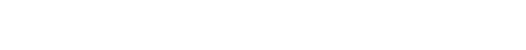教室紹介
教授挨拶
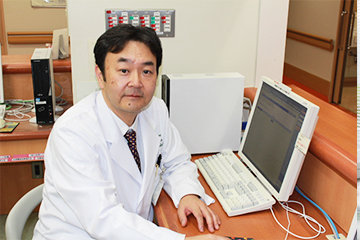
山形大学医学部産科婦人科学講座は2023年に開講50年を迎えようとしています。初代教授の廣井正彦名誉教授が苦労して立ち上げた教室は、二代目教授である倉智博久先生(現・大阪母子医療センター総長)に引き継がれ大きく発展し、現在、山形県内の基幹施設産婦人科のほとんどが山形大学産科婦人科学講座の出身者になっており、また、全国各地で活躍しています。私は2014年11月からこの教室を預かっておりますが、山形県内の産婦人科医療を支え、世界と競争できる人材を育成する、を教室のミッションとして取り組んでおります。直近の3年間をみましても、毎年4~5名が山形県内の産婦人科研修プログラムで産婦人科研修を開始しており、これからの産婦人科医療を支えていく有望な人材が集まってきています。教室員全員が産婦人科診療に真摯に取り組み、医学部生・研修医への熱意ある教育を継続してきた結果と考えています。
さて、産婦人科の領域は生殖・内分泌医学、周産期医学、女性ヘルスケア、婦人科腫瘍学と4つの分野に大きく分かれますが、山形大学ではそのすべての分野の専門医(認定医)が大学に在籍し、診療や研究を行っています。この4分野以外でも、臨床遺伝学、婦人科細胞診、内視鏡手術といった産婦人科診療に大きく関係する領域の専門医(認定医)が在籍しています。これは、産婦人科を学ぼうとする医学生や新たに専門医を目指そうという医師に素晴らしい教育を提供できるだけではなく、大学病院で診療をうける方々に最良の治療を提供できる環境です。
産婦人科は思春期から老年期まで、女性の生涯を支える診療科であり、その時々のライフスタイルや社会環境に応じて最適な医療を提供していく必要があります。産婦人科の各専門領域が細分化されてしまうと、同じ診療科であるにもかかわらずそれぞれが独立したものとなって、融通が利かなくなるといった弊害が生じがちです。我々の教室では、各専門領域ごとにカンファレンスを行った情報を全体のカンファレンスでもきちんと共有して診療にあたっています。この体制が、専門領域に偏りすぎない広い視野をもった医師を育成していくことにつながっていますし、このような連携の良さ、風通しの良さが我々の教室の強みであると考えています。
広い視野を持った医師が専門分野を超えて連携し、学生・研修医のみなさんには最適な学びの場を、産婦人科の病気で悩まれている患者さんにとっては安全で最良の場を、これからも提供していきたいと思います。
医学博士
所属学会:日本産科婦人科学会(理事)/日本婦人科腫瘍学会(常務理事)/日本産科婦人科手術学会(理事)/日本臨床細胞学会(代議員)/日本女性医学学会(代議員)//婦人科悪性腫瘍研究機構/日本癌治療学会/日本癌学会/日本産科婦人科内視鏡学会/日本人類遺伝学会/日本生殖医学会/日本周産期・新生児医学会 など
資格:日本産婦人科学会専門医・指導医 /婦人科腫瘍学会専門医・指導医 /日本臨床細胞学会細胞診指導医 /日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医